3 調査票 裁判員制度に関する世論調査
平成17年2月
1.裁判に対する関心等
最初に,裁判に対する関心について伺います。
Q1 〔回答票1〕 あなたは,裁判の制度や裁判の手続,判決などに関心がありますか。この中から1つだけお答えください。
| (22.7) | (ア) | 関心がある |
| (28.7) | (イ) | どちらかといえば関心がある |
| (28.8) | (ウ) | あまり関心がない |
| (17.4) | (エ) | 関心がない |
| ( 2.4) | わからない |
Q2 〔回答票2〕 あなたは,裁判の制度や裁判の手続,判決などに対して,どのような印象を持っていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| ( 7.6) | (ア) | 信頼できる |
| (28.9) | (イ) | 縁遠い存在である |
| (58.6) | (ウ) | 問題の解決に時間がかかる |
| (32.2) | (エ) | わかりにくい |
| ( 2.1) | その他( ) | |
| ( 2.8) | 特にない | |
| ( 3.9) | わからない |
2.裁判員制度に対する認識
次に,裁判員制度について伺います。
Q3 〔回答票3〕 裁判員制度は,平成16年5月に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」により,平成21年5月までにスタートします。この制度は,殺人など法律で定められた一定の重大な刑事事件の裁判に国民が裁判員として参加して,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合,どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。あなたは,このような裁判員制度が始まることを知っていますか。この中から1つだけお答えください。
| (37.2) | (ア) | 知っている | →SQへ |
| (34.3) | (イ) | ある程度知っている | →SQへ |
| (28.5) | (ウ) | 知らない | →Q4へ |
(Q3で(ア),(イ)と答えた者に)
SQ 〔回答票4〕 では,裁判員制度が始まることを何から知りましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,486)
| (63.5) | (ア) | 新聞 |
| ( 7.1) | (イ) | 雑誌 |
| (89.1) | (ウ) | テレビ |
| (10.5) | (エ) | ラジオ |
| ( 3.2) | (オ) | インターネット |
| ( 0.9) | (カ) | ポスター |
| ( 1.0) | (キ) | パンフレット |
| ( 0.4) | (ク) | 講演会,説明会 |
| ( 0.7) | (ケ) | 学校の授業 |
| ( 0.1) | (コ) | タウンミーティングなどのイベント |
| ( 5.9) | (サ) | 家族や友人との会話など |
| ( 1.7) | (シ) | 仕事を通じて |
| ( 0.5) | その他( ) | |
| ( 0.1) | わからない |
(全員に)
Q4 〔回答票5〕 あなたは,殺人など法律で定められた一定の重大な刑事事件の裁判に国民が裁判員として参加することで,裁判や国民の意識などがどのように変わると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (27.0) | (ア) | 法律の専門家ではない国民が裁判員として参加しやすいようにするため,刑事裁判の手続や判決が国民にもわかりやすくなる |
| (14.3) | (イ) | 本来の仕事やそれぞれの家庭などを持つ国民が裁判員として参加しやすいようにするため,刑事裁判が速く行われるようになる |
| (27.6) | (ウ) | 裁判に国民の感覚が反映され,司法に対する国民の理解や信頼が深まる |
| (31.2) | (エ) | 犯罪や治安のことを自分たちの問題として考えて解決していこうという国民の意識が強まる |
| (39.3) | (オ) | 裁判員として参加する国民は法律の専門家ではないため,有罪・無罪や刑の内容について,適切ではない判断が出るおそれがある |
| (10.4) | (カ) | 特に変わらない |
| ( 1.3) | その他( ) | |
| (10.8) | わからない |
3.裁判員制度と職業や日常生活との関わり
次に,裁判員制度と職業や日常生活との関わりについて伺います。
Q5 〔回答票6〕 裁判員が参加する刑事裁判は,本来の仕事やそれぞれの家庭などを持つ国民が裁判員として参加しやすいようにするため,できるだけ早く終わるような仕組みになっています。あなたが裁判員になる場合,裁判所に行く日数を多くて何日までにしてもらいたいですか。この中から1つだけお答えください。
| (11.8) | (ア) | 1日 |
| (35.6) | (イ) | 2〜3日 |
| (20.1) | (ウ) | 4〜5日 |
| ( 7.9) | (エ) | 6〜10日 |
| ( 6.7) | (オ) | 10日を超えてもよい |
| ( 2.6) | その他( ) | |
| (15.2) | わからない |
「資料A」を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。
Q6 〔回答票7〕 裁判員が裁判所に行く日数は,それぞれの事件の内容などにより変わりますが,多くは数日で終わるのではないかと見込まれています。あなたが裁判員として,例えば全部で3,4日裁判所に行くことになった場合のことを考えてください。記憶が薄れないようにするためには,できるだけ間に日を置かないで裁判を進めることが望ましいとされていますが,あなた自身は,自分の仕事のことなどを考えた場合,毎日裁判所に行った方が都合がよいですか,それとも,ある程度日を置いて裁判所に行った方が都合がよいですか。この中から1つだけお答えください。
| (10.6) | (ア) | 毎日 |
| (29.1) | (イ) | 週に2,3日程度 |
| (42.0) | (ウ) | 週に1日程度 |
| ( 2.8) | (エ) | それ以上 |
| (15.5) | わからない |
Q7 〔回答票8〕 会社に勤めるサラリーマンなどについては,裁判員の役目を果たすために仕事を休んだことなどを理由に,会社が従業員に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。これ以外に,さらにサラリーマンなどが裁判員の役目を果たしやすいようにするため,あなたは,どのようにすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (44.1) | (ア) | 会社の経営者や幹部の間に,裁判員制度への理解を広める |
| (53.1) | (イ) | 裁判員の役目を果たすために仕事を休んだ場合は,会社が有給休暇扱いにする |
| (29.4) | (ウ) | 裁判員の役目を果たすために収入が減った場合,その分を補てんする任意加入の保険や共済などの仕組みを普及させる |
| (27.5) | (エ) | 裁判所が,裁判員に選ばれた人の仕事の都合を考えて,裁判員が裁判所に行く日程を決める |
| ( 1.8) | その他( ) | |
| (10.7) | わからない |
Q8 〔回答票9〕 では,お年寄りの介護や子供の養育をしている人が裁判員の役目を果たしやすいようにするため,あなたは,どのようにすればよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (27.1) | (ア) | 配偶者や親戚,近所の人たちの間に,裁判員制度への理解を広める |
| (59.5) | (イ) | 必要なときに,介護施設や育児施設を利用しやすくする |
| (35.8) | (ウ) | 裁判員の役目を果たすために介護施設や育児施設を利用した場合の費用を補てんする任意加入の保険や共済などの仕組みを普及させる |
| (28.2) | (エ) | 裁判所が,介護や養育をしている裁判員の都合を考えて,裁判員が裁判所に行く日程を決める |
| ( 2.4) | その他( ) | |
| ( 9.6) | わからない |
4.守秘義務,裁判員の保護
「資料B」を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。
Q9 〔回答票10〕 あなたは,このように法律で守秘義務が定められていることについて,どう思いましたか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (57.7) | (ア) | 「評議の秘密」を守らなければならないのは,評議で自由に意見を言うことができるようにするためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う |
| (54.8) | (イ) | 「評議の秘密以外の秘密」を守らなければならないのは,個人のプライバシーなどを守るためであることがわかったので,このような秘密を守ることは大切であると思う |
| (13.8) | (ウ) | 証人が公開の法廷で話した内容などが守秘義務の対象にならないことは意外である |
| (22.9) | (エ) | 秘密を守らなければならないということは負担になると思う |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| ( 8.2) | わからない |
「資料C」を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。
Q10 〔回答票11〕 あなたは,裁判員のプライバシーや身の安全などの保護について,このような仕組みになっていることで安心しましたか,それとも不安ですか。この中から1つだけお答えください。
| (15.1) | (ア) | 安心した |
| (25.0) | (イ) | どちらかといえば安心した |
| (29.5) | (ウ) | どちらとも言えない |
| (14.9) | (エ) | どちらかといえば不安である |
| ( 9.4) | (オ) | 不安である |
| ( 6.2) | わからない |
5.裁判員制度における刑事裁判への参加意識
次に,裁判員制度における刑事裁判への参加について伺います。
Q11 〔回答票12〕 裁判員は,20歳以上の国民の中から,くじ等の方法で,原則として無作為に選ばれ,裁判員に選ばれた場合,その役目を果たすことは,義務とされています。あなたは,裁判員として刑事裁判に参加したいと思いますか。この中から1つだけお答え下さい。
| ( 4.4) | (ア) | 参加したい | →SQaへ |
| (21.2) | (イ) | 参加してもよい | →SQaへ |
| (34.9) | (ウ) | あまり参加したくない | →SQbへ |
| (35.1) | (エ) | 参加したくない | →SQbへ |
| ( 4.4) | わからない | →Q12へ |
(Q11で(ア),(イ)と答えた者に)
SQa 〔回答票13〕 あなたが裁判員として刑事裁判に参加したい(参加してもよい)と思う理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=532)
| (48.5) | (ア) | 国民として協力したいと考えるから |
| (28.8) | (イ) | 刑事裁判がこれまでよりよくなると思うから |
| (13.3) | (ウ) | 自分が参加して,これまでの刑事裁判を変えたいと思うから |
| (24.6) | (エ) | 刑事裁判に興味があるから |
| (29.9) | (オ) | 今後,自分の人生において役にたつかもしれないから |
| (32.1) | (カ) | 犯罪防止や治安に関心があるから |
| (29.7) | (キ) | 国民の義務だから |
| ( 1.7) | その他( ) | |
| ( 0.2) | 特にない | |
| ( - ) | わからない |
(Q11で(ウ),(エ)と答えた者に)
SQb 〔回答票14〕 あなたが裁判員として刑事裁判に参加したくないと思う理由は何ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,454)
| (22.8) | (ア) | 裁判員制度の意義をよく知らないから |
| (23.9) | (イ) | 裁判員制度の仕組みをよく知らないから |
| (46.5) | (ウ) | 有罪・無罪などの判断が難しそうだから |
| (19.9) | (エ) | 仕事に差しさわりがあると思うから |
| (10.0) | (オ) | 家事に差しさわりがあると思うから |
| (12.2) | (カ) | 健康上の問題などがあり,参加することが難しそうだから |
| (23.6) | (キ) | 関係者から逆恨みされないか心配だから |
| (23.7) | (ク) | 裁判や事件というものに関わりあいたくないから |
| (17.4) | (ケ) | 面倒そうだから |
| (46.4) | (コ) | 人を裁くということをしたくないから |
| ( 2.9) | その他( ) | |
| ( 0.8) | 特にない | |
| ( 0.3) | わからない |
(全員に)
Q12 〔回答票15〕 裁判員は,法律の専門家ではなく,また,本来の職業やそれぞれの家庭などを持つ国民であるため,裁判員が参加する刑事裁判は,できる限りわかりやすく,かつ,速く行われるように,さまざまな工夫がなされています。あなたが,裁判員になって刑事裁判に参加する場合,裁判官,検察官,弁護人に対して,特にどのようなことを望みますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (76.2) | (ア) | わかりやすい言葉を使ってもらいたい |
| (40.4) | (イ) | たくさんの書類を読まないでも済むようにしてもらいたい |
| (36.7) | (ウ) | 図面などを活用して,わかりやすい説明をしてもらいたい |
| (37.6) | (エ) | 裁判にかかる時間を短くしてもらいたい |
| (26.1) | (オ) | 法律の専門家ではない裁判員に対しても,敬意を持って接してもらいたい |
| (33.5) | (カ) | 有罪・無罪などを決める議論の場では,十分に意見を言う機会を与えてもらいたい |
| ( 0.4) | その他( ) | |
| ( 3.6) | 特にない | |
| ( 4.7) | わからない |
6.国への要望
次に,国への要望について伺います。
Q13 〔回答票16〕 あなたは,裁判員制度について,どのようなことを知りたいですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (35.1) | (ア) | 裁判員制度が導入される意義 |
| (33.8) | (イ) | 裁判員が取り扱う事件の種類や内容 |
| (40.7) | (ウ) | 裁判員の具体的な役目 |
| (30.0) | (エ) | 裁判員と裁判官が一緒に話し合いをして,有罪・無罪や刑の内容を決める方法 |
| (32.8) | (オ) | 裁判員が選ばれる方法や手続 |
| (17.2) | (カ) | 裁判員に選ばれる確率 |
| (31.0) | (キ) | 裁判員になることを辞退できる理由 |
| (20.2) | (ク) | 裁判員として裁判所に行く日数 |
| (42.1) | (ケ) | 裁判員の安全やプライバシーの保護 |
| (16.9) | (コ) | 裁判員の日当 |
| (24.2) | (サ) | 会社に勤めるサラリーマンなどが裁判員になる場合の会社との関係 |
| ( 0.6) | その他( ) | |
| (10.5) | 特にない | |
| ( 4.1) | わからない |
Q14 〔回答票17〕 あなたは,今後,国は,裁判員制度の意義などを広く国民に周知するため,どのような広報や啓発のための活動をすべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (84.5) | (ア) | テレビ・ラジオを利用した広報 |
| (60.6) | (イ) | 新聞・雑誌などを利用した広報 |
| (16.2) | (ウ) | バナー広告などインターネットを利用した広報 |
| ( 8.8) | (エ) | 広報用ビデオの上映や貸出し |
| (19.4) | (オ) | 国民が参加するなどして実際の裁判と同じように裁判の手続をやってみる「模擬裁判」の実施 |
| (26.0) | (カ) | パンフレットの配布 |
| (16.3) | (キ) | 公共施設など人目につく場所へのポスターの掲示 |
| (18.2) | (ク) | 講演会や説明会の開催 |
| (12.5) | (ケ) | 法律の専門家と国民とが直接対話するなどの国民対話型イベントの開催 |
| (35.1) | (コ) | 中学校や高校などにおける教育 |
| (13.9) | (サ) | マスコミの取材などに対する積極的な対応 |
| ( 0.7) | その他( ) | |
| ( 3.5) | わからない |
Q15 〔回答票18〕 裁判員制度は,国民が裁判員として刑事裁判に参加する制度であるため,国民一人一人が法や司法制度に対する理解を深めていくことが大切ですが,特に,将来を担う若い世代の人たちが,法や司法制度に関心を持つことが重要です。このため,法務省では,法教育(法律の専門家ではない人たちが,法や司法制度の価値を理解し,法的なものの考え方を身に付けるための教育)などに力を入れていくことにしています。あなたは,特に若い世代の人たちが,法や司法制度に関心を持つためには,どのような法教育に関する取組みが重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (44.3) | (ア) | 裁判を傍聴する機会を増やす |
| (53.2) | (イ) | 裁判官,検察官,弁護士といった法律の専門家が学校などに出向き,法や司法制度について講義する機会を増やす |
| (39.5) | (ウ) | 法教育の教材を充実させる |
| (34.0) | (エ) | 教師に対する研修を充実させる |
| ( 0.9) | その他( ) | |
| (10.3) | わからない |
最後に,ご回答を統計的に分析するために,あなたご自身のことについて伺います。
<<フェース・シート>>
F1〔性〕
| (48.0) | 男性 |
| (52.0) | 女性 |
F2〔年齢〕 あなたのお年は満でおいくつですか。
| ( 3.9) | 20〜24歳 |
| ( 5.5) | 25〜29歳 |
| ( 7.2) | 30〜34歳 |
| ( 8.2) | 35〜39歳 |
| ( 7.6) | 40〜44歳 |
| ( 8.6) | 45〜49歳 |
| (10.1) | 50〜54歳 |
| (11.8) | 55〜59歳 |
| (11.0) | 60〜64歳 |
| ( 9.8) | 65〜69歳 |
| (16.3) | 70歳以上 |
F3〔本人職業〕 あなたのご職業は何ですか。
(職業の内容を具体的に記入してから,下の該当する項目に○をつける。)[ ]
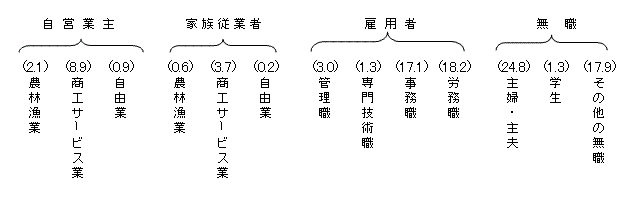
F4〔回答票28〕〔裁判傍聴経験の有無〕 あなたは,裁判を傍聴したことがありますか。
| ( 5.6) | (ア) | 1回傍聴したことがある |
| ( 4.8) | (イ) | 2回以上傍聴したことがある |
| (89.6) | (ウ) | 傍聴したことはない |
「資料A」
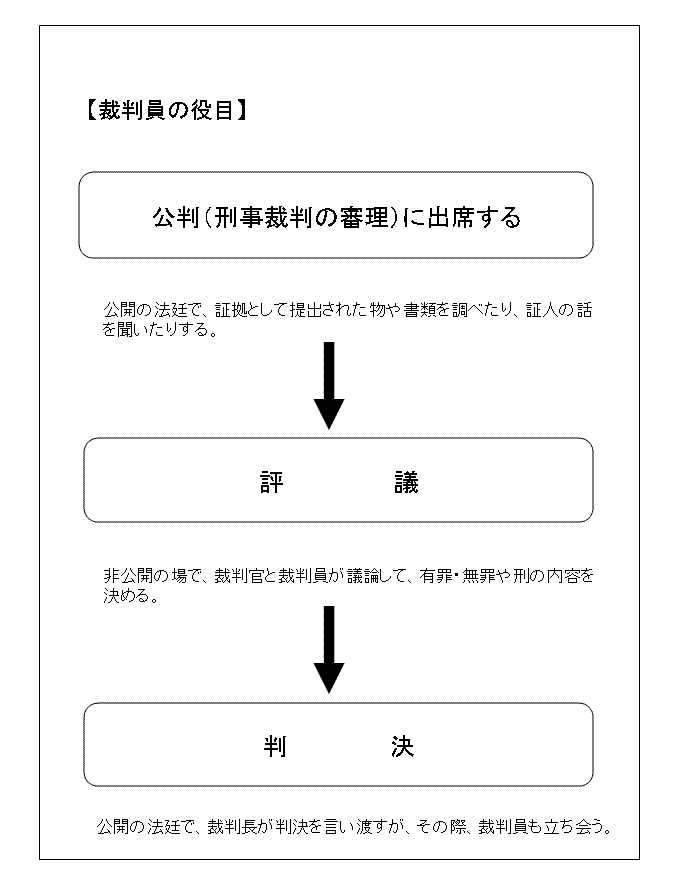
「資料B」
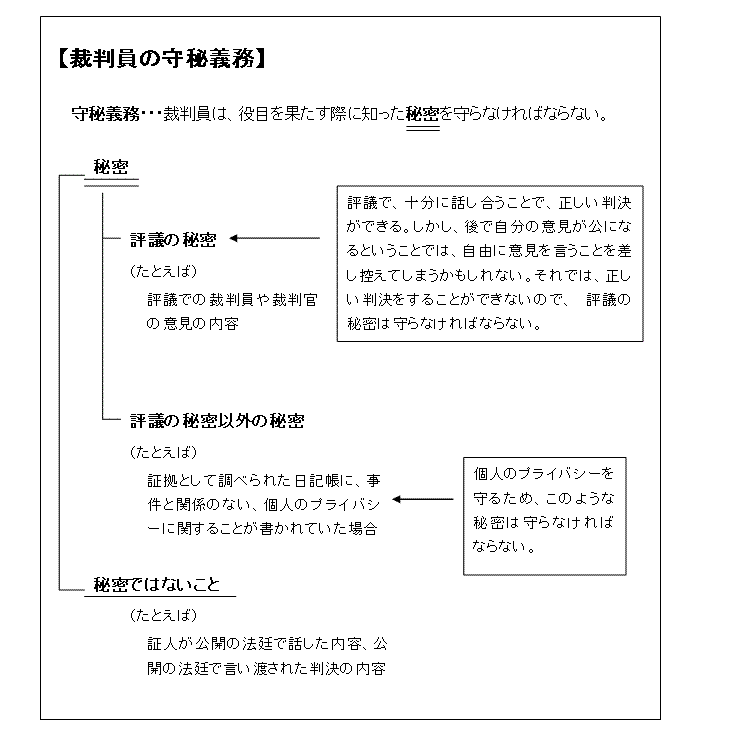
「資料C」
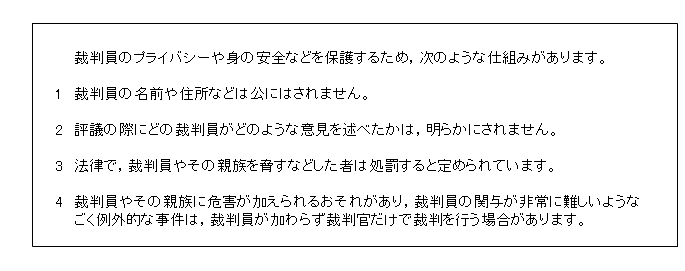
目次 | 戻る
